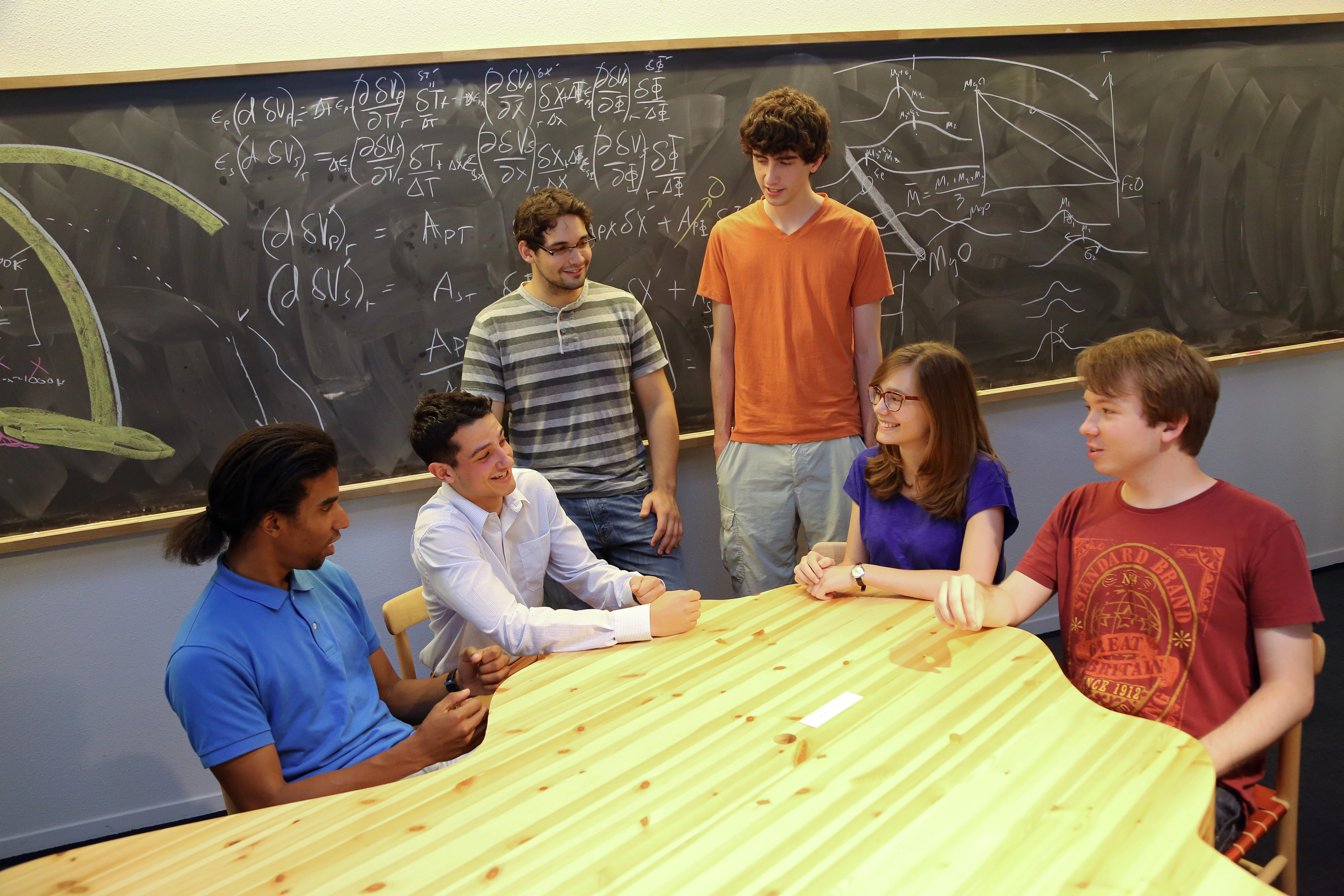どんな研究?
地球温暖化の主な原因とされる二酸化炭素(CO2)。その排出量を削減する方法の1つとして有望視されているのが、「メタネーション」と呼ばれる技術です。これはCO2と水素を反応させて、天然ガスの主成分であるメタン(CH4)を合成する方法です。グリーン水素の利用とCO2の循環利用を実現することで、持続可能なエネルギー源を供給する方法として注目されています。
CO2分子は、炭素(C)と酸素(O)が頑丈に結合しているため、これを引き離すためには高温の熱エネルギーが必要になります。さらに、メタネーション反応で発生する熱により反応温度は上昇するため、メタン合成に有利とされる低温条件を保つことが本質的に困難になります。加えて、高温では反応を進めるはたらきをする触媒に余計な炭素が付着して反応の効率を下げたり、一酸化炭素(CO)のような不要な副生成物が発生するなどの問題があります。
そこで、東京科学大学の野崎智洋(のざき・ともひろ)教授率いる研究チームは、触媒にプラズマを作用させることで、低温でメタネーションを高効率で実現する新しい反応システムを開発することに成功しました。

ここが重要
研究チームが着目したのは、「低温プラズマ」です。プラズマとは気体分子(原子)から電子が分離して電気伝導性を持った状態のことで、固体、液体、気体に次ぐ「物質の第四の状態」と言われています。プラズマの中には、電子とイオンだけでなく、分子間の結合が切れてばらばらになった中性の粒子(ラジカル)など多くの活性種が含まれているのが特徴で、その中でも水素原子と振動励起されたCO2が低温でメタン生成反応を促進することを明らかにしました。
低温プラズマを使えば高価な貴金属触媒を使わずに、廉価で工業的に多用されるNi/Al2O3触媒でもメタン化反応を低温で実現できます。Ni/Al2O3触媒の場合、230℃でのメタン収率はわずか2.3%でしたが、低温プラズマを利用すれば同じ230℃で27.2%と、約11倍の変換効率を達成できたのです。メタン合成の低温化に成功したおかげで、不要な副生成物の生成も抑えることができ、もちろん高温にするための余計なエネルギー消費を低減できるため、従来技術より少ないエネルギー消費で合成メタンを供給することができます。
今後の展望
今回開発されたプロセスは、低炭素社会の早期実現に貢献する技術です。さらに、水素原子が触媒反応を低温で促進する反応の理解が深まったことで、今後は高温・高圧が必要とされてきた化学反応でも必要なエネルギーを減らせる技術につながる可能性があります。たとえば、農業には欠かせない窒素肥料の原料となるアンモニアを、空気と水から合成するプラズマ技術が既に報告されています。現在よりエネルギー効率が高くなれば、ハーバー・ボッシュ法よりも低炭素かつ地産地消に適した窒素固定化技術として普及することが期待されます。
研究者のひとこと
プラズマの力を使うことで、低い温度でCO2を都市ガスなどとして使えるエネルギーのメタンに変えることができました。これまで高温が必要だった反応がよりマイルドな条件かつ低エネルギー消費で進むようになったのは大きな前進です。この成果が、地球環境にやさしい未来のエネルギー社会の実現につながることを願っています。
(野崎智洋:東京科学大学 工学院 機械系 教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口