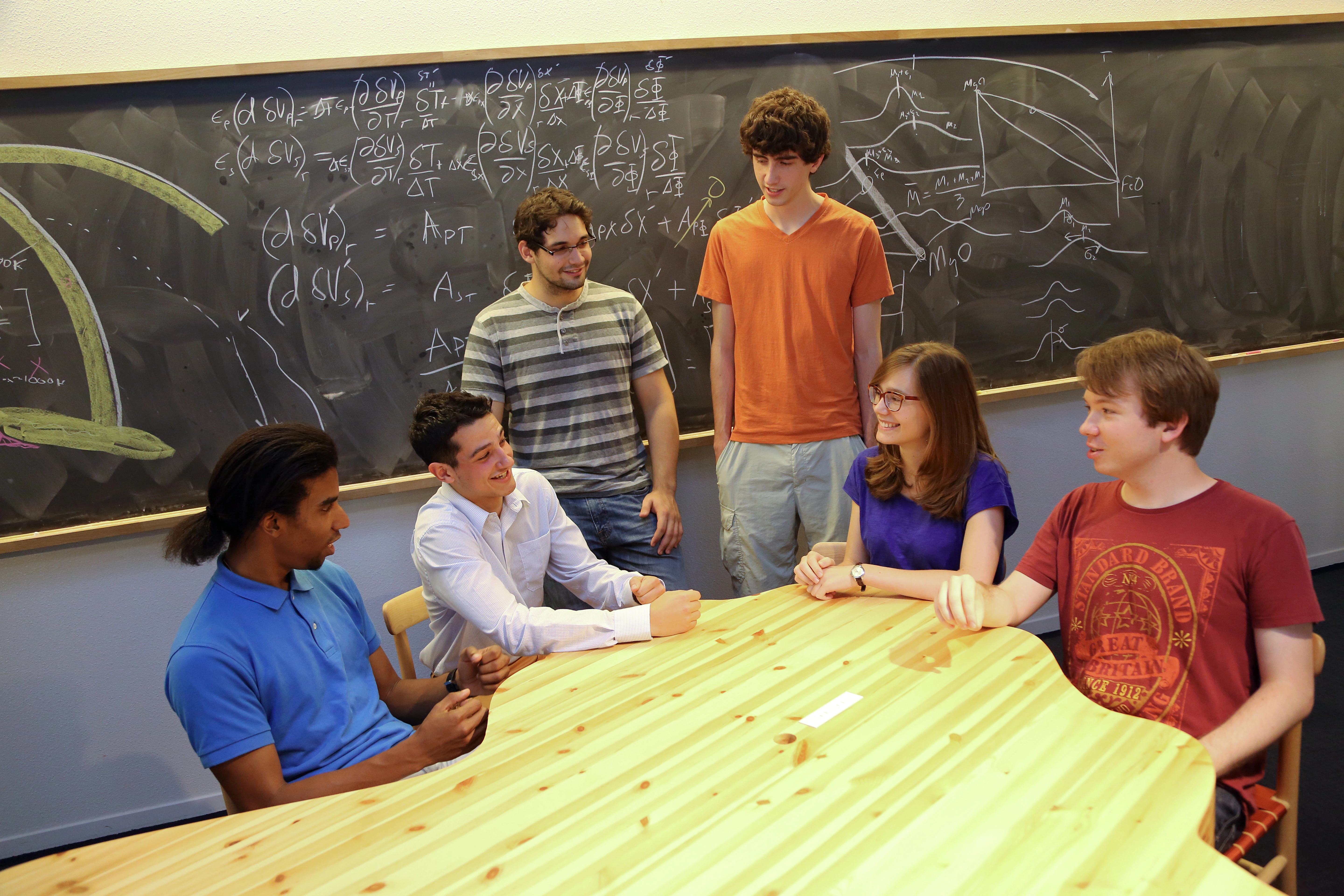どんな研究?
植物は光のエネルギーを使って栄養をつくる「光合成」をしています。でも、光が強すぎると、かえって植物はダメージを受けてしまいます。
ダメージを受けると、たとえば、光を受け取る仕組み(光合成装置)が壊れたり、活性酸素という細胞を傷つける有害な物質が発生したりします。これは、植物細胞内のpH(酸性・アルカリ性の度合い)の変化と関連していて、植物にとって、生存や成長を脅かす大問題です。
そこで植物は、光を吸収しすぎないようにブレーキをかける仕組みを使って、自分の身を守っています。このしくみは、専門的には非光化学的消光(NPQ: Non-Photochemical Quenching)と呼ばれています。

これまでの研究で、NPQの調節にはDLDG1というタンパク質が必要であり、強い光を受けると、DLDG1にスイッチが入るかのように働きだして、葉緑体の中のpHを整えることがわかっていました。そして、葉緑体の内部でエネルギー生産を担うATP合成酵素は、pHに応じて生産するエネルギー量を調整しており、pHの値が適切でなくなると、その活動が低下していくことが知られていました。
ところが、DLDG1が存在しているのは、葉緑体の外側です。それに対してATP合成酵素は葉緑体の内側のチラコイド膜と呼ばれるところにあります。つまり、DLDG1とATP合成酵素は植物細胞の内部ではそれぞれが異なる場所に存在しています。これまで、強い光を受けた時に、お互いがどのように連携するのか謎でした。
ここが重要
東京科学大学(Science Tokyo)の増田真二(ますだ・しんじ)教授を中心とする研究チームは、DLDG1とATP合成酵素が実際に「協力」して植物を守っていることを確かめ、その協力のメカニズムを明らかにしました。
強い光によってチラコイド膜の内側は酸性化、外側はアルカリ化し、このpH差によってATP合成酵素が働きます。このpH差の形成は、主にチラコイド膜を隔てた水素イオンの移動によるものと考えられていますが、葉緑体の外側に存在しているDLDG1も水素イオンを葉緑体の中から外へ、もしくは外からは中へ移動させることで、このpH差を適切にしているのです。
その結果、ATP合成酵素の周囲が適切なpH環境に変化し、再びエネルギー生産を行うことができるようになり、余分な光エネルギーはNPQにより安全に消去できるのです。このように、DLDG1とATP合成酵素は連携して必要以上に強い光を受ける環境でも光合成を適切に行う仕組みを作り上げていました。これこそが、植物の強い光に対する防御の仕組みだったのです。研究チームは、この仕組みこそが、光の強さが大きく変わるような環境の中でも、植物の成長を支えるためにとても大切であることを明らかにしました。
今後の展望
この研究では、「DLDG1とATP合成酵素の双方が存在することでpHがうまく調整される」という新たなしくみが明らかになりました。この発見は、環境変動に強い植物をつくるためのヒントになります。
たとえば、暑さや乾燥、強い日差しなど、過酷な自然環境でもしっかり育つ作物を開発するには、こうした植物自身の「防御システム」を理解して活かすことが重要です。また、光合成の効率を高める技術にも応用できる可能性があり、地球環境にやさしい農業や食料生産にも貢献が期待されます。
研究者のひとこと
土に根を張る植物は、思っている以上に巧みに環境と向き合っています。今回は、葉緑体の外と中にある物質同士が見えないところで協力していることがわかり、私たちも驚きました。このしくみをもっと深く理解することで、未来の農業や食の安全にも役立てていきたいです。
(増田真二:東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口