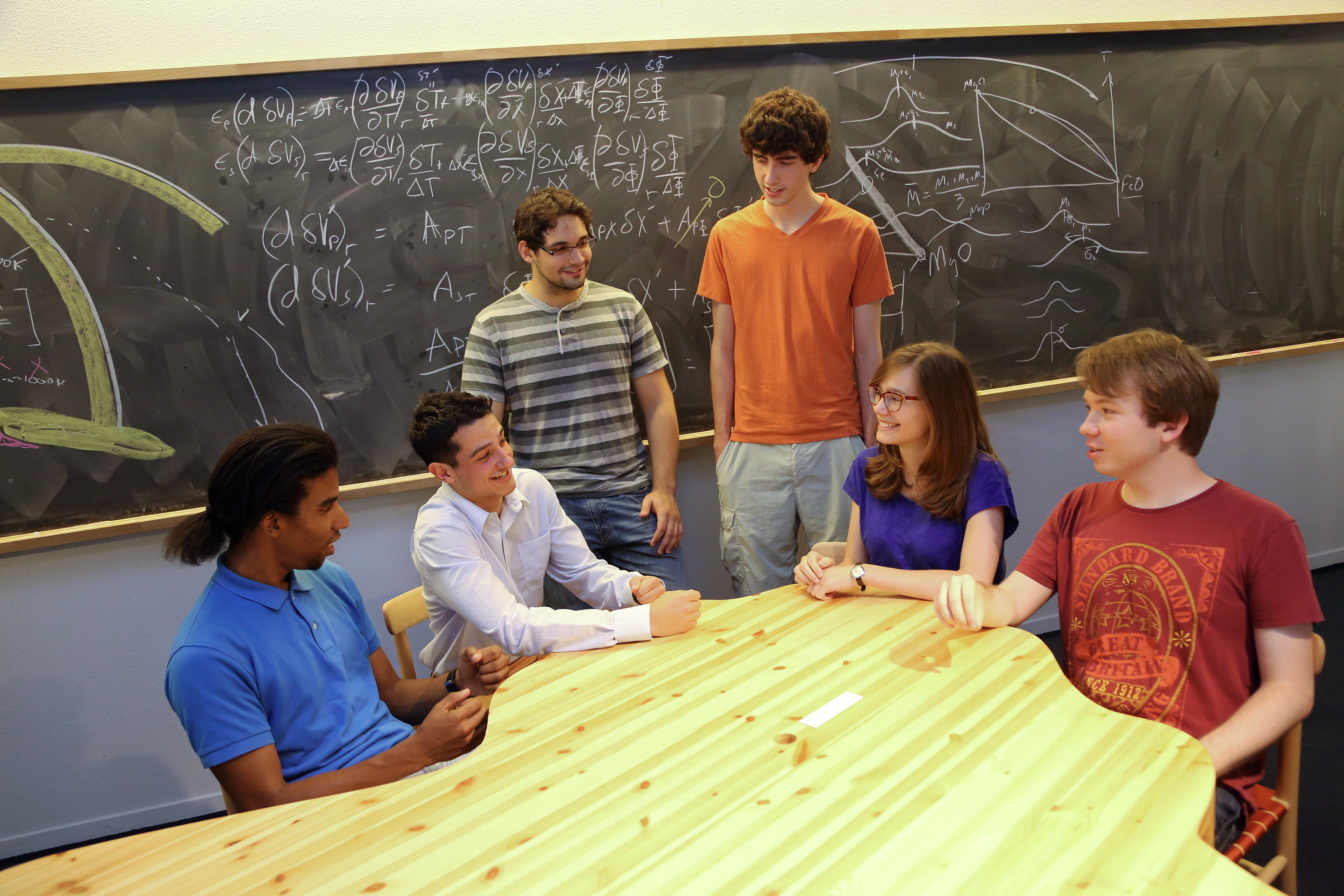どんな研究?
わたしたちが音を聞くとき、耳の中にある血管条という組織が重要な役割を果たします。血管条は、音を電気信号に変えるために必要な電圧を生み出す「耳の中の電池」のような存在で、脳が電気信号を受け取って音だと認識する聴覚のしくみを支えています。
その血管条は、SLC26A4という遺伝子によって作られるペンドリンというたんぱく質がなければ働きません。そして、このSLC26A4という遺伝子に異常があると、血管条がうまく働かなくなり、難聴が起こるのです。しかし、同じ遺伝子異常でも難聴の度合(症状の重さ)には個人差があり、その理由はよくわかっていませんでした。

東京科学大学(Science Tokyo)の伊藤卓(いとう・たく)講師らは、SLC26A4遺伝子に異常があるマウスの血管条を観察するなかで、メラニン(黒い色素)がたまった場所にマクロファージ(免疫細胞)が集り、炎症が起きていることに気づいていました。しかし、たまったメラニンが炎症を引き起こしているのか、それとも、炎症の結果としてメラニンがたまったのかがわからなかったのです。
そこで、伊藤講師らの研究チームは、色素がないマウスと、色素を持つマウスの両方に同じ遺伝子異常をもたせて、難聴の進み方や耳の中のマクロファージの反応を比べてみることにしました。
ここが重要
色素を持つマウスは皮膚の新陳代謝などにともなって耳の中にメラニンがたまり、それを掃除しようとマクロファージが活性化していました。マクロファージとは、体内をパトロールして、ウイルス・細菌・壊れた細胞などの異物を見つけて「食べる」免疫細胞です。異常があると判断するとサイトカインという信号物質を出して、他の免疫細胞に知らせ炎症反応を引き起こします。
しかし、こうした免疫の働きが過剰になると、かえって組織を傷つけてしまいます。実際に色素を持つマウスではマクロファージが活性化して炎症が強くなり、難聴も進行しました。一方、色素がないマウスでは、マクロファージあまり活性化せず、炎症もおだやかで、難聴の進行もゆるやかでした。
こうした違いは、3D画像やコンピュータ解析によって裏付けられました。また、メラニンがたまる原因は作りすぎではなく、うまく分解できないことだったことも分かりました。
今後の展望
メラニンの量や性質は、体質や遺伝などの要因によって人それぞれ異なります。したがって、炎症を抑える薬やメラニンの分解を助ける治療法も、個別に合わせた方がより効果的だと考えられます。将来的には、一人ひとりの体質に合った難聴治療が可能になっていくと考えられます。
また、耳の中の免疫細胞の働き方やメラニンとの関係をさらに詳しく調べていけば、難聴以外の耳の病気や、さらには神経の病気ともつながる共通のしくみが見つかる可能性があります。
研究者のひとこと
メラニンといえば肌や髪の色の話だと思われがちですが、耳の中でこんなに重要な役割をメラニンが果たしているとは驚きでした。これからは“見た目に見えない色”の働きにももっと注目していきたいですね。(伊藤卓:大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科学分野 講師)
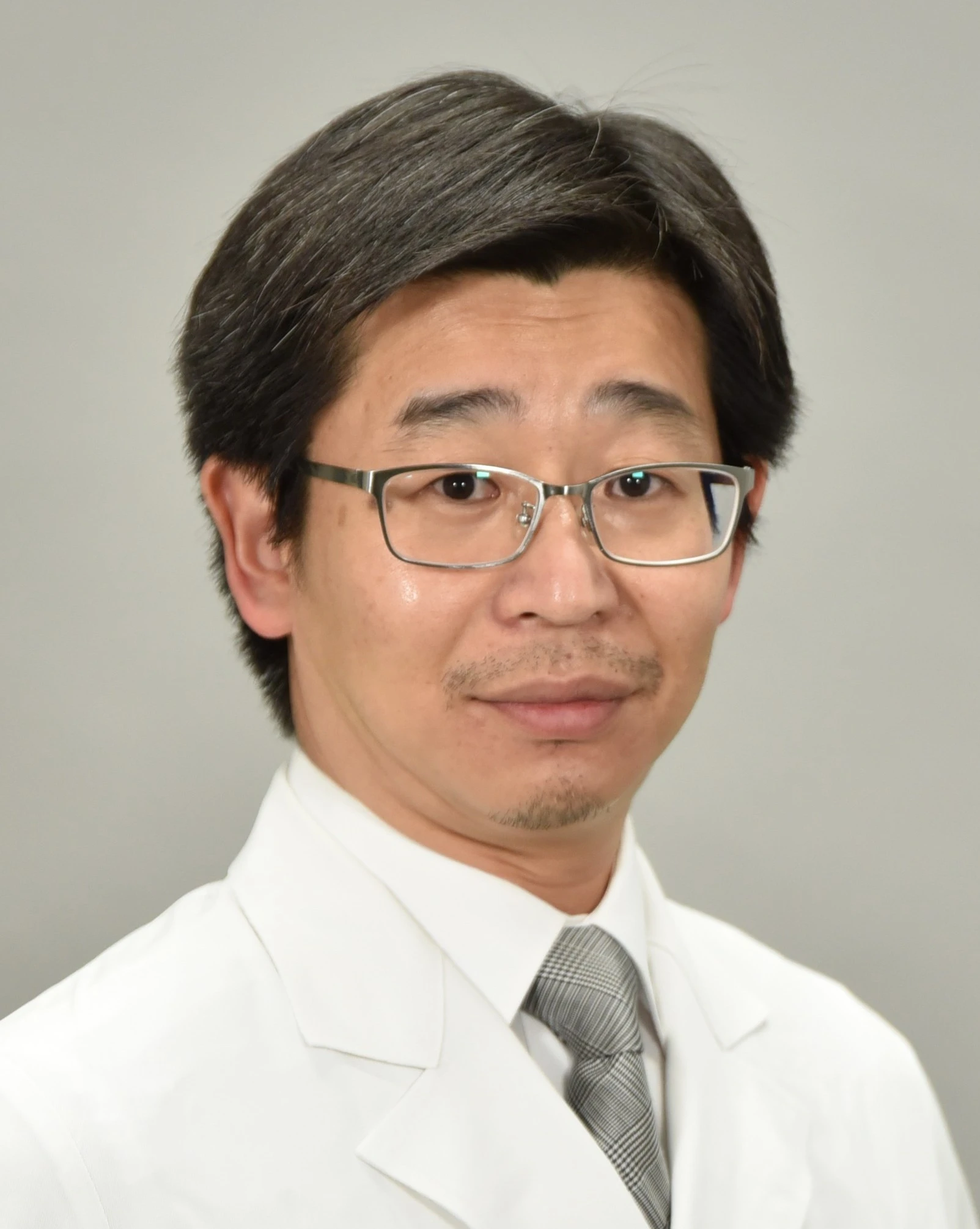
この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口